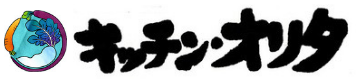カレーは20種以上のスパイスを使わないと作れないと信じている人が多いのですが、実は次の6種類プラス辛味スパイスがあれば簡単にできます。市販のカレールーでは出来ない本格的な味に、はまってしまうことうけあいです。
このレシピでは辛味がなく、とてもマイルドで小さい子供でも大丈夫です。
スパイシーな料理が好きな人には物足りないかもしれません。子供の分を取り分けた後、チリパウダー、クミンパウダー、シナモンパウダーなどを加えて火にかけ味の調節をしてください。ターメリックは絶対あとから加えないこと。
ルーは冷凍できますので、倍量作って残りは冷凍してください。

材料(4人分)
ネパール風カレーは、インドカレーよりスパイスと油の量が少なく日本人にとっては食べやすい料理です。
- 鶏肉 500g(骨付のままカレー用にカットする)
- 玉ねぎ 大2個(400g 細かめの乱切り)
- トマト 中2個(200g 皮は湯むきして乱切り)
- グリンピース ひとつまみ
- 塩 小1
- 醤油 大2
- 粉末ブイヨン 大1
- 油 適量
- 水 カップ2
- ターメリックパウダー 小2
- クミンパウダー 小2
- コリアンダーパウダー 小1
- シナモンパウダー 小2
- カルダモン 8粒(皮をむいてかるくつぶす)
- クローブパウダー 小2
- 辛味スパイス(チリパウダー)
- 辛味スパイス(グリーンペッパー)
- 辛味スパイス(レッドペッパー)
- おろしにんにく 大1
- おろししょうが 大1
作り方
① 一口大に切った鶏肉にパウダー状のスパイス、皮をむいてつぶしたカルダモン、にんにく、しょうが、塩、醤油、油を入れよく混ぜ合わせておく。
② フライパンに油を熱し、玉ねぎを茶色くなるまで炒める。(さきにレンジで加熱しておくと早いです。)
③ ②に鶏肉を入れて炒める。
④ 鶏肉の色が変わったてきたら、水、トマト、ブイヨンを入れる。(辛味スパイスは好みで加える。)
⑤ ふたをして10分。ふたをとってから20~30分中火で煮る。
⑥ 煮詰まってきたらグリンピースを入れ火を止める。
⑦ 白いごはんにかけても良いがサフランライスならなお良い。
カレーも立派な薬膳です
香辛料の薬効についての面白い研究発表がありましたのでご紹介いたします。
『香辛料のヒト脳循環と脳高次機能に及ぼす影響』というタイトルで、東京大学の丁先生らが2002年8月千葉県幕張メッセで、開催された『和漢医学学会』で発表されたもので、以下にその内容を要約します。
脳梗塞などの脳血管障害や痴呆の症状が発生する以前から、脳を循環している血液量が少なくなっていることがわかっていました。この原因として、動脈硬化が起こって血液が流れにくくなっているか、血管が収縮する作用が長時間にわたって働いているか、いろいろ考えられるでしょうが、脳血管障害や痴呆の症状をおこりにくくするには、要は脳の血液量を減らさないようにすれば良いということなのです。
実験として、ヒトの頭に脳の中の血液量を測る測定器を取り付け、いろいろな食品や香辛料を食べる前と食べた後とで血流を測定しました。
その結果カレーには年齢に関係なく前頭部の脳循環血流量を増加させる作用があることがわかりました。カレーには約30種類の香辛料が配合されており、薬品ではなく食品ですが、このような作用がはっきりと認められたことは驚きです。
次に、カレーの中の香辛料のうち何にもっとも脳循環血流量を増加させる作用があるかを調べるために、50種類以上の個々の香辛料について、各々2gを食べる前と後とで脳血流量の変化を測定しました。
その結果、カルダモンに安定した作用が認められ、脳血流量の増加は持続的で、食後1時間目で最大7%も増加しましたが、このために頭痛や吐き気などの副作用はなかったと報告しています。
一方、玉ねぎには逆に脳血流量を減らしてしまうような作用が見られましたが、その理由についてはわかっていません。
このような香辛料による脳の機能の活性化はどういう作用によるものなのか、今のところ解明されておらず、今後の研究の成果を待たなければなりませんが、いづれにしても高齢化社会にすでに突入してしまったわが国において、香辛料が生体に及ぼす作用についての研究結果が待たれます。香辛料を普段の食卓に活用することが、食事による予防医学を実践する方法の1つであることは間違いないでしょう。